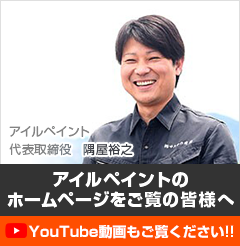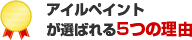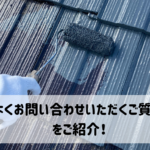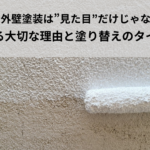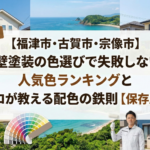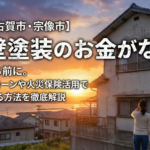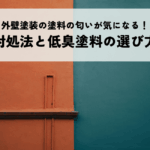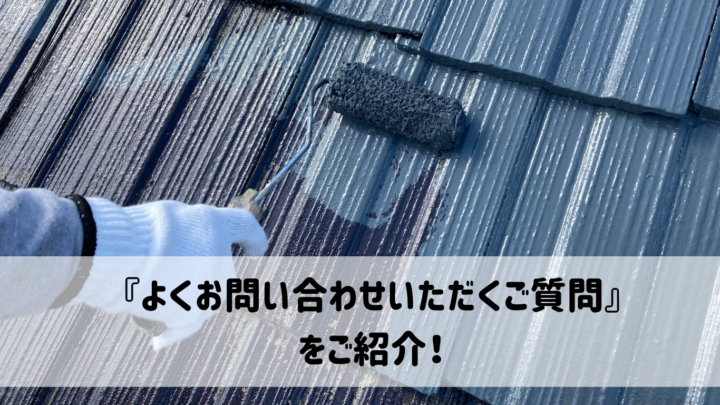
2026.01.24 更新
『よくお問い合わせいただくご質問』をご紹介
皆さまから実際に『よくお問い合わせいただくご質問』をご紹介いたします。 〇〇坪ですが費用はいくらですか? 多くの皆さまが一番気になるであろう費用に関するお問い合わせです。 申し訳ございません。 残念ながら坪数では費用を想定することが出来ないため お答えすることが出来ないのです。 弊社では、外壁の面積=実際に塗る面積を算出し それを元にお見積り費用をご提示させていただいております。 まったく同じ坪数でも、お家の形、窓の数・大きさ、ベランダの有無などにより 外壁面積は大きく変わります。 業者によっては、坪あたりいくらと金額を設定している場合もあるかもしれませんが それが適正な価格なのかどうか… 外壁面積に応じて塗料の必要な量が異なるため 適正な量が塗布されるのか? 塗布回数は適正なのか? など心配になります。 また、使用されている外壁材により最適な塗料や塗る回数も変わるため 一概に坪数では価格を決められないのです。 まずは、お見積りを取得し、詳細な説明を受けられることをおすすめ致します。 工事をするのに一番ベストな季節はいつですか? こちらも良くお問い合わせをいただきます。 もしくは『工事が出来ない季節はありますか?』 お答えは…いつでも大丈夫です! 塗装工事の大敵は、天候です。 どんな季節でも雨が降ると工事は滞ってしまいます。 しいて言えば、梅雨の時期は工期が長引くことがある為 なるべく早く終わらせたい場合は、梅雨時期を避けるのも良いかもしれません。 もうひとつ大切なのが気温です。 塗料の施工上の注意事項として 『塗装場所の気温が5℃以下の場合塗装を避けて下さい』 と記載されている場合がおおくございます。 九州地方では、年間数日ほどしかないかと思いますが 日中の気温が低温の場合、工事をお休みさせていただく場合がございます。 洗濯物は干せますか? 基本的に工事期間中は、洗濯物を外に干すことは出来ません。 塗料の付着や、臭い移りのリスクがあるためです。 工事休業日など例外的に可能な場合もあるため、担当職人にご相談ください。
続きはコチラ



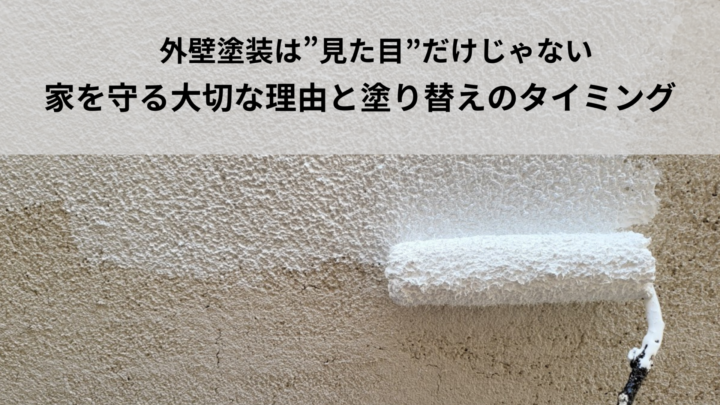

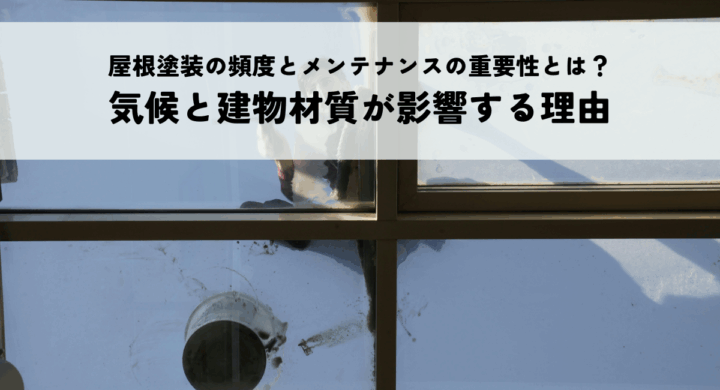
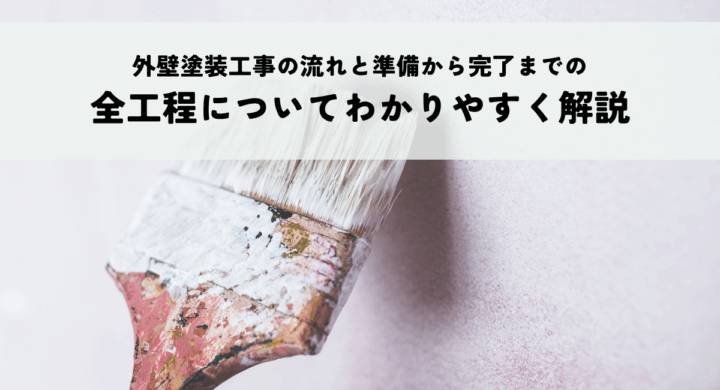

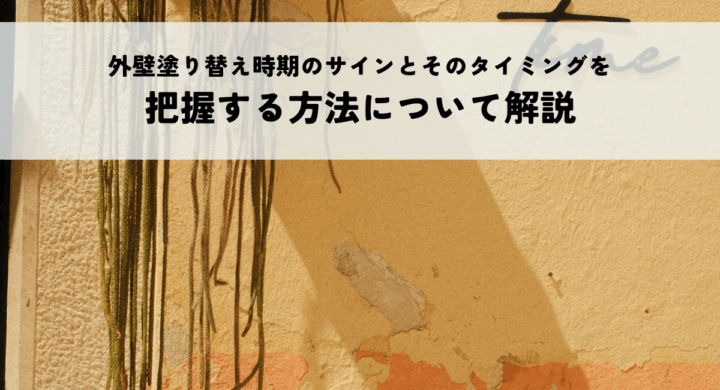
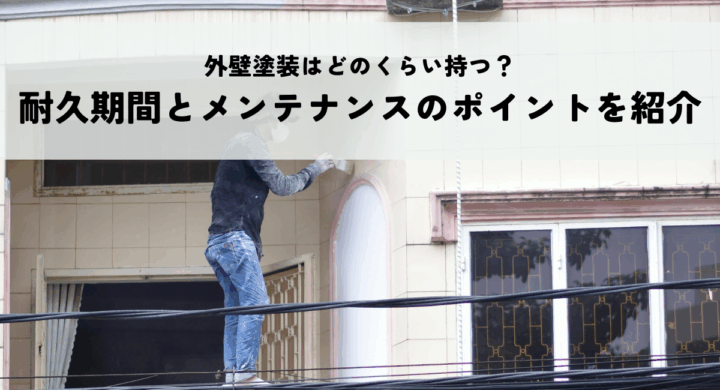
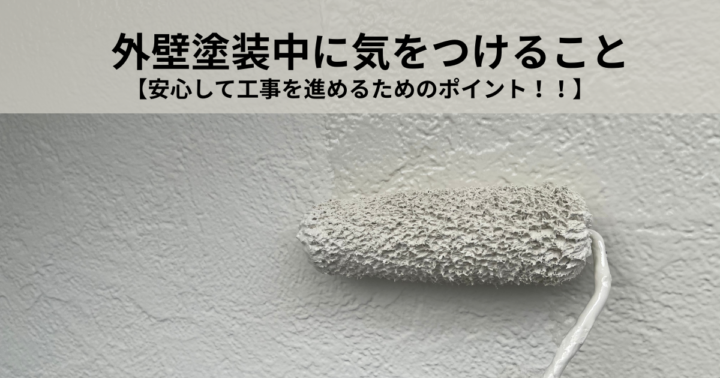
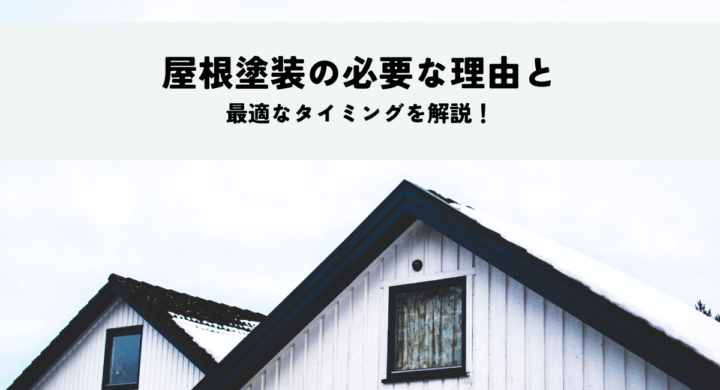
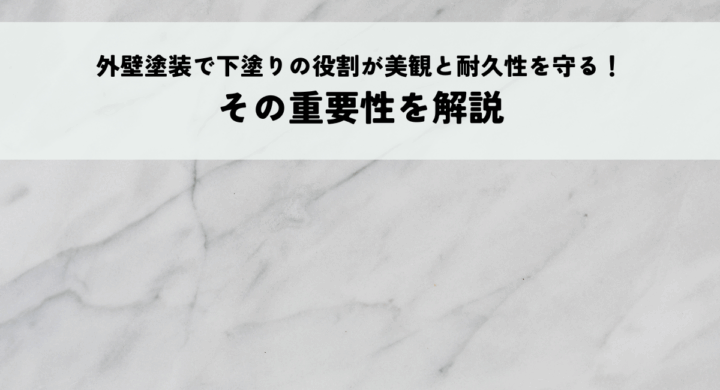
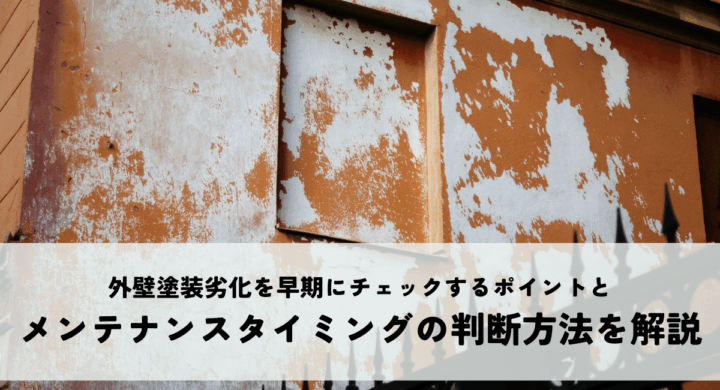
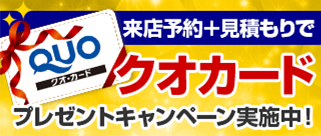

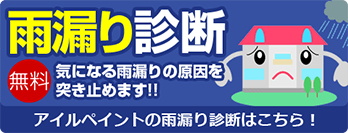
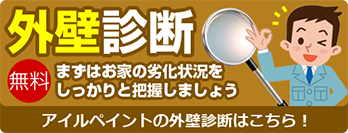
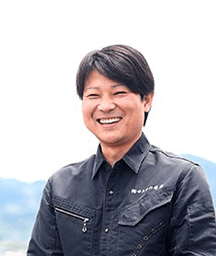




 福津市古賀市 宗像市で
福津市古賀市 宗像市で